

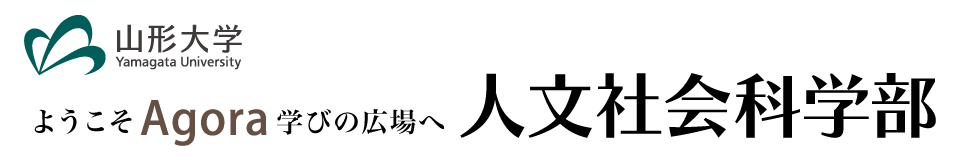


ホーム > 研究所 > やまがた地域社会研究所:安達峰一郎研究資料室 > 資料室ブログ
このブログは、高校生・大学生、一般の方に、外交官・常設国際司法裁判所裁判官として活躍した安達峰一郎の「国際法にもとづく平和と正義」の精神を広く知って頂くために設けました。安達峰一郎に関するイベント等の情報、安達峰一郎の人となりや業績等に関わる資料紹介、コラムやエッセイ、今日の国際関係に関わる記事等を随時配信していきます。
投稿日:2022年3月16日
2022年2月24日ロシアのウクライナ侵略の報に接して、1931年9月18日に勃発した満州事変を想起した人も多いことと思います。前者はプーチン大統領が決定し、後者は関東軍の謀略によるものという違いはあるにせよ、当時日本は国際連盟理事会常任理事国、今日ロシアは国際連合安全保障理事会常任理事国で、両国とも常任理事国です。国連総会でロシア非難決議が採択されたものの、まだ停戦が見通せない現在(3月9日)ですが、以下では、安達峰一郎との関係で、関東軍が暴走していた満州事変期における国際連盟日本代表部に関係するトピックを書き留めておきたいと思います。
満州事変当時、安達はオランダのハーグで常設国際司法裁判所長の要職にあり、国際連盟における満州事変対応は、安達の後任の駐仏大使・国際連盟日本代表である芳澤謙吉を中心にした国際連盟日本代表部で行われていました。
安達から芳澤への交代は1930年半ばのことで、内閣は濱口雄幸・立憲民政党内閣、外相は幣原喜重郎で第二次幣原外交の時期です。芳澤は長く中華民国特命全権公使を務めた対中国政策のエキスパートですから、国際連盟に日中紛争事案が提出されたときの対応を考えてのことであろうと推測されます。当時は、濱口内閣の前の田中義一・立憲政友会内閣時代に、山東出兵を三度行うなど、対中強硬外交が行われ、日中関係は悪化するばかりでした。第二次出兵後の済南事件(1928年5月3日に起こった済南での武力衝突事件)については、南京政府から国際連盟に提訴がありましたが、代表権は北京の中華民国政府にあるという日本側の主張もあって、承認されませんでした。この件の対応にあたっていたのは国際連盟事務局次長の杉村陽太郎ですが、安達は当時の連盟日本代表でしたから、ともに苦労していました。
このような背景があって芳澤が駐仏大使・国際連盟日本代表に抜擢されたと推測されますが、これとほぼ同時期に、国際連盟日本事務局長として安達を補佐した佐藤尚武が駐ベルギー大使に転じ、澤田節蔵(1884-1976)が佐藤の後任となります。
澤田のフランス勤務は3回目のことで、日本国際連盟協会を組織するなど連盟での活動を待望していた国際連盟派の外交官です。
『澤田節蔵回想録』(『日本外交史人物叢書 第19巻』、2003年、ゆまに書房)の中で、澤田はこの時期の国際連盟外交について、欧州少数民族問題は「先輩石井菊次郎、安達峯一朗、佐藤尚武各大使が苦労し続けられた問題であるが」、「芳沢氏は、理事会にもたびたび出席の経験を持っておられたが、連盟関係のことには詳しくなく、ことに欧州少数民族問題については全て私に任せ切りであった」(128頁)と、書いています。
これに対して「安達大使は仏国勤務が長く、連盟創立の功労者で、連盟における功績は各方面で頗る高く評価されていた。厄介きわまる少数民族問題の処理に当っても、新鋭優秀な佐藤局長の補佐のもとに次から次と持上がる各種案件を見事に処理された」(139頁)、「安達大使は大いに日本の声価を高められた」(140頁)とことのほか高く評価しています。
さらに澤田は、満州事変時の国際連盟対応について次のように述べています。連盟日本代表は「英語か仏語によって遺憾なく我が立場を説明し、会議参加国の多数をわが国の主張に同調せしめるだけの外国語の能力を備えていなければならない」(152頁)。芳澤大使は中国問題については「人後に落ちざる権威者」で、満州問題を扱うには適任であったが、「ところが満州問題の如き大政治問題を取り扱う会議では普通の標準で英仏語が堪能だという程度では足りず、言葉のうえからも真に英仏人の敬意を招くぐらいでなければならない。この見地からすると芳沢さんの表現力は十分とはいえなかった」(152頁)。そして、1931年11月にパリで開催された連盟理事会における仏外相A.ブリアン議長と芳澤とのやりとりに言及して、そのチグハグな様子が伝えられています。
要するに芳澤大使は中国問題の権威で専門性においては最適任であったが、国際連盟の事業には詳しくなく、英仏語能力も十分でなかったということです。さらに付け加えると、安達がブリアン外相の腹心L.ルシュールとともに取り組んでいた「日仏議員親善会」結成による政治的提携強化の動きも、芳澤への交代によって途切れたのではないかと推測されます。
安達は事変案件が常設国際司法裁判所に諮問されたときには「日支ノ満州ニ於ケル関係ニ付テハ殆ト無知」だから日本の立場を理解せしめることは困難だと危惧していましたから、満州問題において卓越したエキスパートであった芳澤が適任であったことはその通りです。しかし、国際連盟との連携や日仏の外交的・政治的提携関係が弱化していたことも否めないのではないでしょうか。そして、この点が日本代表部が苦労することになった一因のようです。
もちろん国際連盟との連携がうまくいかなかったもっと大きい理由は、連盟の関与を避けて日中二国間交渉にこだわった幣原外相・日本政府と、連盟の威信をかけて早期解決を模索する連盟理事会との対立にあります。10月に入って関東軍の暴走が止まらない中で、A.ブリアンが議長を務める連盟理事会は、連盟非加盟国アメリカのオブザーバー参加を決めますが、これにより、日本側との対立が激しくなります。世評とは異なるかもしれませんが、幣原はもともと連盟外交のような会議外交よりも伝統的な二国間外交志向が強い外交官です。他方、ブリアンとフランス側が日本軍の即時撤兵と早期解決を強く求めたのは、前年1930年9月にドイツ国会選挙でヴェルサイユ体制打倒を掲げるナチスが台頭しており、満州事変が同じく常任理事国ドイツによるポーランド回廊占拠のような事態の先例になることを恐れたからでもあります。
このとき日本代表部は、日本政府と幣原外相に対して、対連盟強硬姿勢を改めるよう意見を提出し、また佐藤はアメリカのオブザーバー参加は「容認」するのが得策ではないか、満洲問題を「連盟ノ範囲内ニ於テ解決スル」ことも必ずしも不可能ではないのではないかと具申します(幣原外相宛電信、1931年10月(19)日)が、奏功しません。
結局、連盟対日本の様相は連盟理事会における調査団(リットン調査団)派遣決定でひとまず収まるのですが、その後の展開はよく知られている通りで(1)、翌1932年秋のリットン報告書では日本軍の行動は「自衛の措置」とは認められず、「満州国」も日本軍と日本の文武官吏の活動なしには成立しなかったとされ、1933年2月24日の連盟総会における勧告書採択の結果、最終的に日本は国際連盟を脱退。このときも澤田は、脱退は日本の国際的孤立を招くと断固反対の立場から、松岡洋右日本代表の「連盟脱退のほか途なし」とする政府への電信送付の中止を強力に求めましたが、叶いませんでした。
以上、澤田の『回想録』によりながら、満州事変期の対国際連盟外交の一コマに触れました。もちろん、謀略によって始められた侵略戦争=満州事変の衝撃は途轍もなく大きいもので、安達が日本代表であったならば、とか、連盟の関与を回避しなければどうであったか、というようなことを超えたレベルのものであったでしょう。関東軍の暴走が制止されない事態の只中で行われた日本の連盟派外交官の孤軍奮闘が報われることはありませんでした。
澤田は、日本の国際連盟脱退が第二次世界大戦への起点になったことを痛恨の思いで語っていますが、これに関連して以下一点のみ簡単に付け加えておきます。日本の国際連盟脱退宣言後は、日仏関係はさらに希薄になります。フランスは、日本脱退に続いて脱退したナチス・ドイツに対抗して、イギリスとともに連盟を維持することに傾注し、ソ連・東欧諸国との関係を強化します(ソ連の国際連盟加盟は1934年9月)。他方、安達大使の後は日仏の政治的連携関係がエアポケットに入った感がありますが、日本陸軍内では、親仏派の上原勇作派の系譜で、事変を契機に主流になった荒木貞夫陸相中心の皇道派が、北一輝に呼応して、連盟脱退を想定し、英米に対抗して日仏同盟を結ぶというプランを進めました。これは、集団安全保障重視のフランスに相手にされるはずがありません。それゆえ、連盟脱退とともに、国際連盟だけでなく日仏関係が持っていた重しもとれて、日本陸軍内ではドイツ駐在武官であった親ナチの大島浩を中心とした親独派が台頭し、日本外交に影響力を振るいます。陸軍内の主導権争いとしては皇道派と統制派のそれが有名ですが、親仏派と親ナチ的な親独派との路線交代も目立たない形で進んだようです。そのあとは、ソ連を仮想敵とした日独防共協定(1936年)から、第二次世界大戦勃発の後、フランス領インドシナ北部進駐とほぼ同時にアメリカを仮想敵国とした日独伊三国同盟(1940年)への途を歩みます(芦田均のところで言及した「日仏同志会」は日仏の政治的提携関係を構築しようとしたもので、その主要メンバーは日独伊接近阻止派です)。その途上で日本は日中戦争(1937年)の泥沼に入り込んでいました。
現在、ロシアのウクライナ侵略に対しては、国連安保理に提出された即時撤退決議案がロシアの拒否権に阻まれたものの、総会が非難決議を挙げ、アメリカを中心に経済制裁が行われています。第二次世界大戦・太平洋戦争に至る大筋を考えると、歴史的状況が異なるとはいえ、「願わくは、1930年代と同じ轍を踏まないことを!」と思わざるを得ません。
余談ですが、満州事変の首謀者が石原莞爾で、満州事変前の三月事件や事変勃発後の十月事件というクーデタ未遂、血盟団事件、五・一五事件などに深く関わったのが大川周明です。両人とも安達と同じ山形県出身者であったことには、なんと言ってよいのか、言葉が見つかりません。
(1) 「満州国」独立宣言(1932年3月1日)の後に起こる「満州国」承認問題でも、日本代表部は、国際連盟との対立を激化させないよう承認の遷延を政府に要請していました。なお、安達は、事変に関する中国の訴えを常設国際司法裁判所で審理することになれば、紛争解決手続に関する連盟規約第15条からしても、また満蒙特殊権益に関しても、日本の主張が受け入れられる見込みはないという趣旨の手紙を、斎藤実首相宛(1932年5月27日)に送っています(柳原正治編『世界万国の平和を期して 安達峰一郎著作選』、東京大学出版会、2019年、所収)。
投稿日:2020年3月27日
芦田は、戦後、東久邇宮内閣の後組閣された幣原喜重郎内閣の厚生大臣に就任します。吉田茂は外務大臣です。1945年10月16日の閣議では、幣原首相は憲法を改正しなくとも解釈による運用で対応できるという態度だったようですが、芦田は現行欽定憲法はポツダム宣言第10項(「民主主義的傾向の復活強化」)と相入れない点があると見ていたようで、閣議では「インテリ層」は改正必至と考えているなどの発言をしています。また、吉田は「外務大臣の権限外」と消極的だったようです(原彬久『吉田茂』、岩波新書、2005年)。
この後松本烝治国務相を中心にして憲法改正要綱が作られるのですが、これは大日本帝国憲法をさほど変えておらず、連合国最高司令官総司令部によって拒否されます。そして、1946年2月3日に提示されたマッカーサー三原則を基に総司令部案が作成されて、13日に日本政府に手渡されます。幣原首相は19日、22日と閣議を開き、受諾決定のもと、3月2日案が作成されます。詳細は省略しますが、この後は総司令部との交渉を経て作業が続けられ、4月17日に憲法改正草案が公表されます。帝国議会で審議が始まるのは6月20日からです(4月10日の衆議院議員総選挙の後、幣原内閣は退陣、吉田内閣が成立しています)。
ここでは9条の発案者はマッカーサーか幣原かといった問題や、マッカーサー三原則に対するケーディス修正の問題(マッカーサー三原則第2原則は「国家の主権的権利としての戦争を廃棄する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としてのそれをも放棄する。……」としていましたが、ケーディス民政局次長の判断で下線部の自衛権放棄の所はカットされて、総司令部案では「第八条 国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス 陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ決シテ許諾セラルルコト無カルヘク又交戦状態ノ権利ハ決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルヘシ」とされたことに関する問題)など、議論の多いテーマには触れません。9条の原型にあたる戦争放棄や戦力放棄、交戦権放棄を規定した総司令部案の受け入れを日本政府が決めたときの議論が重要だと考えると、1946年2月22日の閣議に注意する必要があるでしょう。
当時の閣議の様子は、通常『芦田均日記 第1巻』(進藤榮一, 下河辺元春編纂、岩波書店、1987年)や入江俊郎法制局次長の記録が参照されますから、ここでは芦田の日記を参照しましょう。そこでは、21日のマッカーサーと幣原の会談で、マッカーサーが憲法改正に関する権限を持つ極東委員会の空気を伝え、「日本の為めに図るに寧ろ第二章(草案)の如く国策遂行の為めにする戦争を抛棄すると声明して日本がMoral Leadershipを握るべきだと思ふ」としたのに対して、 幣原は「leadershipと云ハれるが、恐らく誰もfollowerとならないだらうと云った」ことなどが伝えられています。幣原はためらいがちのように見受けられますが、マッカーサーの態度に「理解ある意見」を述べたとのことです。
松本国務相は不満を述べ、ドイツ・南米の例を引きつつ「外より押つけた憲法」への危惧を表明しています。安倍能成文相は第一条の主権在民は帝国憲法と「principleに於て」かなり「相反する」ものであり、「戦争抛棄の如きも亦現憲法と多大の相違ありと思ハる」と述べたようです。
これに対して芦田は次のように述べたとのことです。
「戦争廃棄といひ、国際紛争は武力によらずして仲裁と調停とにより解決せらるべしと言ふ思想は既にKellog Pact(不戦条約)とCovenant(国際連盟規約)とに於て吾政府が受諾した政策であり、決して耳新しいものではない。敵側は日本が此等の条約を破つたことが今回の戦争原因であつたと言つてゐる。又旧来の欽定憲法と雖、満洲事変以来常に蹂躙されて来た。欽定憲法なるが故に守られると考へることは誤である。…」
さすがに反軍主義の自由主義者にして、国際連盟外交を経験した国際主義者です。「押しつけ」とはいっても、かつて日本は国際連盟規約と不戦条約に署名し「国策遂行の為めにする戦争」の放棄を受諾していたのだから、草案を受諾しない理由はないということでしょう。想像でしかありませんが、この時安達が存命であれば同じような言葉を発したのではないでしょうか。安達は、1920年代末の日本において、戦争違法化と集団安全保障構築など国際主義の流れの先端にいた外交官です。資料的裏付けがあるわけではないですが、安達と芦田の関係も考慮してこのように想像力を働かしてもおかしくはないように思います。また、芦田の発言がなんらかの影響を持ち、議論の結果「かくて内閣案が一決」(入江俊郎)したのであれば、必ずしも英米系とは言えない安達・芦田の国際主義の系譜が果たした役割を再評価してよいのではないでしょうか。
この後、芦田は衆議院において帝国憲法改正案委員会委員長となり憲法審議を進めます。ここで有名な(第9条第2項冒頭の「前項の目的を達するため」の挿入などに関する)「芦田修正」の問題が出てくるのですが、その真相はともかく、近年の研究が指摘するように、この頃の芦田の考え方は、国連憲章の精神と整合的に憲法第9条を捉え、講和後に国連加盟が実現されたとき、日本は自衛権と自衛のための戦力を保有し、集団安全保障に貢献するというものだったでしょう。
しかし、戦争違法化と集団安全保障の安達の構想が満州事変によって打ち砕かれたように、芦田の構想も日本国憲法施行(1947年5月3日)直前から始まる米ソ冷戦によって変容を迫られます。朝鮮戦争勃発後の芦田の再軍備論などには触れませんが、これは別として、米ソ冷戦の終結後、米中新冷戦の時代と言われる今日でも、安達と芦田の国際主義もまた戦後日本の原点を構成するものとして押さえておくことは必要でしょう。
投稿日:2020年3月24日
「日仏同志会」は、坂本龍馬の甥の長男で、東京帝国大学法学部卒業後南満州鉄道株式会社(満鉄)に入社し、1929年満鉄パリ出張所長として赴任した坂本直道(1892-1972)がイニシャチブをとったようです。坂本は、1932年夏、国際連盟日本代表になった松岡洋右に、連盟における日本の孤立化を危惧して、日仏議員友好連盟のようなものを提言した(和田桂子・松崎硯子・和田博文編『満鉄と日仏文化交流誌『フランス・ジャポン』』、ゆまに書房、2012年)のですが、松岡は国際連盟総会でリットン調査団報告に基づく勧告を拒否すると啖呵を切って退場しました。しかしフランスを去る時になって、日本の孤立を避けるため、坂本に日本に対する支持者を拡げる宣伝活動をするよう依頼したようです。大見得を切ったものの、内心では後悔していたのでしょう。
こうして坂本が曽我祐邦子爵に働きかけて1934年7月に設立されたのが本部を東京に置く「日仏同志会」です。総裁に徳川家達、会長に曽我を配し、「日仏関係の有力者」をメンバーとして、フランス下院内の「親日政治家」と日仏間の政治的・経済的提携を促進することを目的としたものでした。芦田は設立準備メンバーの一人で、坂本とともに理事として入っています。石井は顧問、この頃駐仏大使であった佐藤も(時期は不明ですが)理事として入ります。
ところで駐仏大使時代の安達が曽我、L.ルシュールとともに作ろうとした「日仏議員同盟会議」の日本側組織には、石井、幣原、新渡戸稲造といったリベラルな国際協調派の貴族院議員が含まれていましたが、どうもこれは、安達が駐仏大使を退任した後、満州事変の影響によるものか、1931年11月のルシュール逝去によるものかわかりませんが、中断したようです。曽我は「日仏同志会」設立発起人会の席上で、発足に至る経緯を説明して、「数年来の企図の実現」を喜び、「一時中絶した「日仏議員親善会」問題を復活せしむべく決心」したことに触れています(松尾邦之助『風来の記』、読売新聞社、1970年)。また、1928年に安達が関与したルシュールとの会談を想起した文章もあります。ですから、安達がコーディネートしていた「日仏議員同盟会議」の後身にあたるのが「日仏同志会」であると捉えてよいでしょう。
なお、「親日政治家」の中心にいたのはC.ペシャンという医師で共和右派の下院議員で、連盟において日本が孤立化しているときに、『国際連盟対日本』(1933年)という冊子を刊行して日本擁護の論陣を張っていたようです。
さて、日本の国際連盟脱退後、陸軍と外務省の中からは日本の脱退に続いたナチス・ドイツと接近する動きが出てきます。坂本たち「日仏同志会」主要メンバーは、これに対して、米英仏との連携をめざしていました。坂本は、自由主義的ジャーナリストの代表格・清沢洌が「見識ある人物」と評していた人物で、松岡(後に外相として日独伊三国同盟締結にあたります)とは別の思惑で動いたようです。芦田について言えば、日本の連盟脱退後も依然として連盟が重要であると考えていたようですから、連盟の中心国フランスとの関係は密にして、連盟や米英との関係をつけておくということでしょうか。
この「日仏同志会」は、日仏文化交流のための仏語雑誌『フランス・ジャポン』をパリの満鉄支部を拠点として刊行します。その編集者には当時読売新聞の特派員の肩書きを持った松尾邦之助(1899-1975)があたりました。松尾は1922年に渡仏し1940年まで滞在した新聞記者、翻訳家、文芸評論家として活躍した人物で、1926年に『日仏評論』(1930年廃刊)という仏語の文化交流雑誌を刊行します。駐仏大使時代の安達はこれを「日本国民の心の奥底」や「精神」を理解させるという難事業に取り組んだものとして激励する手紙を書いており(紅ファイル1-138)、感激した松尾がこれを『日仏評論』に掲載しています。
なお、『フランス・ジャポン』の寄稿者には、文学者を除くと、石井、佐藤、杉村といった連盟派で駐仏大使の経験者、芦田や長谷川如是閑のような自由主義者がいました。清沢洌のインタビュー記事もあります。雑誌はフランスに日本理解を深めさせることを目的としたようですが、反枢軸、反軍部の自由主義系ジャーナリストたちも寄稿していたのです。
以上のように見てくると、安達が駐仏大使時代に手がけていた「日仏議員同盟会議」や日仏文化交流支援は、満州事変と国際連盟脱退後、「日仏同志会」として形を変えて受け継がれていたように思えますが、「日仏同志会」が設立されたころ、PCIJ判事としてオランダの地にあった安達は1934年8月に病に倒れ、12月28日に亡くなります。『フランス・ジャポン』の第4号は、安達の死によって「日本の最も著名な外交官であり、司法官であり、政治家の一人が失われた」と訃報を掲載しています。
芦田は東京での安達の追悼会(1935年2月18日)に出席し、日記に次のように記していることを紹介しておきましょう。
「安達博士は矢張り一種の才物であったことを思ふ。然し僕は生まれ変つて来なけれバあんな人にハなれない」。(『芦田均日記 1905-1945 第3巻』、柏書房、2012年、684頁)。
芦田は安達に対して格別の畏敬の念を抱いていたようです。
さて、これから後の出来事、つまり、日中戦争の開幕、国際連盟の無力化と第二次世界大戦の勃発、日独伊三国同盟と太平洋戦争へ、といったことは割愛して、一足飛びに戦後のGHQによる占領の時期に移ります。
投稿日:2020年3月19日
戦後再建に貢献した三人の外交官出身の首相のうち、幣原は対米協調外交、吉田は対英協調派で有名ですが、外交官時代の芦田は、外務省の中では「フランス派」とは言えなくともそれに近い位置にあり(内政史研究会『鈴木九萬氏談話速記録』、1974年)、また安達、佐藤尚武、杉村陽太郎といった国際連盟派に近い(矢嶋光『芦田均と日本外交』、吉川弘文館、2019年)位置にいたようです。
ちなみに、第一回国際連盟総会が1920年に開かれた後、連盟外交を実務的に支える帝国事務局をどこに置くか(ジュネーブか別の都市か)で議論がありました。在仏大使館勤務になった佐藤が、連盟の仕事は在ロンドン大使ではなく在仏大使(石井です)が担当することが至当であり、事務局も駐仏大使と密に連絡し、パリ大使館を通じた情報入手をする必要もあると主張して、事務局をパリに置くようになったとのことです(佐藤尚武『回顧八十年』、196-197頁)。佐藤も杉村も在仏大使館勤務を経験して帝国事務局や国際連盟事務局で活躍し、日本の連盟脱退後は駐仏大使を務めますから、国際連盟派と在仏大使館の間には情報交換と人のネットワークが形成されていたように見えます。このネットワークを意識して、安達と芦田との「つながり」を見ておきたいと思います。
芦田均は、1912年外務省に入省後、1914年ロシアに勤務、ロシア革命勃発後、1918年に在仏大使館勤務となり、パリ講和会議には安達と同様日本全権随員として参加します。また、1920年9月に石井菊次郎が駐仏大使として着任後は、石井の下で、国際連盟総会等様ざまな国際会議に出席しています。その後、1923年2月に本省勤務となり、1925年9月に在トルコ大使館に一等書記官として赴任し、1930年7月には駐ベルギー大使館に参事官として勤務します。なお、この時期にまとめた研究は東京帝国大学から法学博士を授与され、1930年『君府(コンスタンチノープル)海峡通航制度史論』として出版されています。多数の著作がある知性派外交官です。
芦田が安達に宛てた書簡が5通残っていますが、それは上記の時期のものです。短い挨拶状やお礼状ですからここで紹介はしませんが、親しみのこもったものです。
さて、芦田がベルギーに赴任した後、国際連盟帝国事務局長として石井や安達を支えた佐藤尚武が駐ベルギー大使に就任します。佐藤は国際連盟総会代表も務め、1931年9月満州事変の勃発後は、安達の後任の駐仏大使・芳澤謙吉(故・緒方貞子氏の祖父です)や国際連盟事務局次長の杉村とともに、国際連盟での対応に追われます。芦田も駐ベルギー代理大使として佐藤を支えるべく奮闘します。しかし、日本政府も外務省も関東軍や軍部を抑制できず、日本と国際連盟との対立が拡大します。この状況で、芦田は、1932年2月の衆議院議員総選挙に立憲政友会から出馬すべく外務省を退職し、当選後は「反軍主義」の政治的リベラリストの雄として帝国議会内外で軍部批判・日本政府批判を繰り広げます。しかし事態は、満州国の樹立と日本政府による承認、リットン調査団の報告、臨時国際連盟総会における勧告決議へと進みます。芦田は日本政府の対応を批判しつつ、連盟脱退阻止の立場から論陣を張りますが、1933年3月政府は脱退通告をします。
日本の連盟脱退後、芦田は代議士としてまた『ジャパンタイムズ』社長として多彩な言論活動を行うとともに、国際連盟を支える国際団体であった日本国際連盟協会(連盟脱退後は日本国際協会と改称)の会員として活動を続け、1934年7月に結成された「日仏同志会」へも参加します。
この「日仏同志会」が、安達が作るべく努力していた「日仏議員同盟会議」(もしくは「日仏議員親善会」)を受け継ぐもののようです。後者には貴族院議員の中でもリベラルな国際協調派が多く含まれているのですが、駐仏大使としての安達がやろうとしていたことがどうなったかという点も気になるので、次回は、戦後改革に一気に進まずに、迂回路をとってこの「日仏同志会」に触れておきましょう。
投稿日:2020年3月17日
先のブログ(「安達峰一郎と石井菊次郎」1~5)の中で、駐仏大使・国際連盟日本代表時代(およそ1928年から1930年半ばまで)の安達が、1928年の不戦条約締結、1929年国際連盟総会における応訴義務(選択条項)受諾表明国の増大、米国の常設国際司法裁判所(PCIJ)への公式参加の可能性など、国際連盟とPCIJ強化を通じた普遍的な紛争処理システムの構築が可能だという展望の下、PCIJ裁判官選挙に立候補する経緯に触れました。
これと関わりますが、この頃、安達はドイツの雑誌Volkermagazin誌から国際連盟10周年記念の寄稿を依頼され、原稿を書いています(1930年1月30日)。次のものですが、大変美しい文章で、安達の夢が語られています。一部ですが先ずこれを見ておきましょう。
「既に25年前、日露戦争の直後に、私は国際連盟の創設を司った考えに似たような考えを持っていました。少し前までは常にヨーロッパと極東を分け隔て、乗り越え難いと考えられていたシベリアが非常にうまく整備されていた為、日露戦争の時ペテルスブルグ政府は数百万人の人間を満州での戦線に送り込むことができました。それ以来の進歩については話すに及びません。数か月前にドイツの飛行船が5日もかからないうちに日本に行くことができたことを想起する必要もないでしょう。40年以上前、私が自分の田舎を出発して首都東京まで来るときに、10日以上の旅を余儀なくされましたが、今日では数時間でその移動が可能になっています。
相対的に見てかなり小さいヨーロッパですが、100年前はほとんど独立した数百の国家に分かれていました。今、私たちはヨーロッパの統一について話し合っています。ここで私が述べているのは自身の見解の一部にすぎませんが、すべてのことを考慮すると、国際連盟が人類の発展において絶対的に必要なものであると考えるに至りました。10年前にアメリカ合衆国の名高いウイルソン大統領が私たちに国際連盟を創設するよう提唱した時に、その機構が強固になることを確信していました。実際、一部の人々の誹謗中傷や嘲りがあったにも拘らず、国際連盟は10年の間、巨大な歩みを示してきました。それはこの機構が諸民族関係の自然な発展に合致したものだったからです。今後10年間で、国際連盟はさらに大きな発展を遂げ、アメリカ合衆国を組み入れるだけでなく、徐々に正常化しながら、ジュネーブのこの偉大な制度に近づいてきているソビエト連邦共和国も組み入れることになるでしょう。
このような考えは私のヨーロッパやアメリカの多くの友人たちによってしばしば述べられてきましたが、専らヨーロッパやアメリカのものではない多くの文明要素を持った私のような人間の熟慮の結果であることからしても、この考えはとりわけ注目するに値します。」(紅ファイル6-318)
安達が日露戦争直後から国際連盟のようなものを考えていたと述べている点は注意しておいてよいと思いますが、主内容は、ヨーロッパを中心に発展してきた国際連盟にはいずれアメリカも、そしてソ連も(不戦条約に調印していますから)加盟するであろうという展望の下に、ドイツ国民に国際連盟への賛同を訴えるというものです。
しかし、安達の見通しは、満州事変と日本の国際連盟脱退、さらにナチス・ドイツによって打ち砕かれます。常設国際司法裁判所長をしていた安達は苦悩に打ちひしがれ、所長退任後、病魔に侵されて1934年12月に亡くなります。
安達が構想していたことが実現するには、第二次世界大戦を経て国際連合の創設を待たなければなりませんでした。不戦条約から日本国憲法第9条への流れは言うまでもありませんが、敗戦国日本の再建において安達の国際主義はどのような経路で受け継がれるのでしょうか。
連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領体制のもとで戦後日本の再建を担った5人の首相のうち3人は幣原喜重郎、吉田茂、芦田均という外交官出身の政治家でしたが、このうち、安達と最も近しい関係にあったのはおそらく芦田均(1887-1959)ではないかと思います。安達の国際主義に近いところで戦後も活躍した外交官出身の政治家で国際連合協会会長も務めた佐藤尚武もいますが、戦後再建に対してより影響力を持ったのは芦田でしょう。こう言われてもピンとこないかもしれませんから、次回以降、芦田に力点をおきながら見ていきましょう。
月別アーカイブ
年別アーカイブ
サイトマップを閉じる ▲