

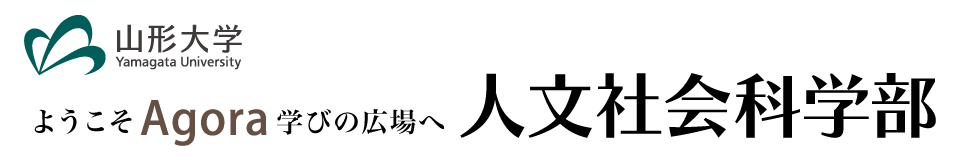


ホーム > 人文社会科学部附属研究所 > やまがた地域社会研究所:安達峰一郎研究資料室 > 資料室ブログ > 1900年パリ万博前後の安達夫妻(その2)―岡村司『西遊日誌』と『安井てつ書簡集』から―
このブログは、高校生・大学生、一般の方に、外交官・常設国際司法裁判所裁判官として活躍した安達峰一郎の「国際法にもとづく平和と正義」の精神を広く知って頂くために設けました。安達峰一郎に関するイベント等の情報、安達峰一郎の人となりや業績等に関わる資料紹介、コラムやエッセイ、今日の国際関係に関わる記事等を随時配信していきます。
投稿日:2019年4月22日
2、子供たち
岡村にはこの当時子供が二人いた。亨と豊である。妻子を日本に残しての留学は「遠島も同然なり」という表現が日誌には出て来るが(1899年(明治32年)10月19日)、妻はもとより可愛い盛りの子供たちと別れての異国生活は、確かに心寂しいものであったろう。
安達夫妻にも幼い子供たちがいた。この当時、長女の功子(イサオ)は日本に残していたが、長男太郎と次女万里子の二人は手元で育てている。岡村とは違った家族団らんの生活をおくっていたと思われる。先にも触れた、パリに着いた直後の岡村の日誌には、安達の子供たちのようすが出て来る。
「午後[中略]、安達峯一郎氏の招飲に赴きぬ。来客は[中略]五人なり。[中略]和洋折衷の御馳走にて珍味いもの多かりき。安達夫婦も座に連なり、下婢二人給仕し、甚だ優渥なる饗応なりき。安達氏の細君は平常洋服を着するものと見え、一見仏人の如し。能く仏語を操る[あやつる]。小児二人、長は男子にて四歳、次は女子なりと云ふ。長男は仏語は能くすれども日本語は知らずと云ふ。これは穏婆[おそらく乳母のこと]、下女等皆仏語を用ゐるが為なり。亦奇と謂ふべし。」(同年10月24日)
最後の「奇と謂ふべし」の「奇」とは、不思議なこと、といった程度のことであろうか。日誌には別の文脈でも出て来るもの言いで、口癖に近く、悪い意味ではない。むしろ、安達の家族がフランス語に慣れ親しんでいることに驚いている感じである。大人より子供の方が言葉に慣れるのが早いことは、帰国子女が稀ではない現代ではよく知られたことであろうが、むしろ年を経ることによってそれらの言葉を忘れてしまうことの方が残念なことである。後のことではあるが、峰一郎も、長男の太郎が日本に帰国してからもフランス語を忘れないように、その勉強を励ましていることは、書簡集でも紹介されている。また、鏡子夫人がフランス語をよくしたことについても、婚姻後の勉強を励ましていることなどから知ることができる。夫人が、峰一郎の同級生から見ても「能く仏語を操る」とされていたことは、興味深いところであろう。
実は、岡村の育児に対する考えが日誌で語られている。日本に残してきた妻郁子宛の日誌であるから、当然といえば当然であるが、岡村の人となりを垣間見ることができることから、短く紹介しておきたい。
岡村は、自身のことを「随分神経質の方」であるという(1900年2月28日)。確かに、「安達の子にスエズにて購入たる玩具を贈」ったり(1899年10月27日)、下宿先の大家にクリスマスの贈り物をする(12月23日)など、細やかな心を尽くしていることを見ることができる。岡村は、そのような自分と、便りに出てくる子供たちの様子を比べ、「親の性質が子に移ること[中略]誠に驚くべし」とし、子供は「成るべくボンヤリと活発に養育するこそ好けれ」という(24日)。「子供等、成るべくぼんやりと育て玉へかし。親に似て神経質なるは宜しからず。」というのが岡村の考えのようである(先の2月28日)。詳しい教育論を展開しているわけではないが、そこに、ルソーのエミールを彷彿させるものを感じるのは私だけであろうか。おおらかに育ってほしいという親の願いを見ることができよう。
安達はどのような教育論を持っていたであろうか。子供たちとのやり取りが書簡として残されているが、詳しく見てみたい事柄の一つである。
月別アーカイブ
年別アーカイブ
サイトマップを閉じる ▲