

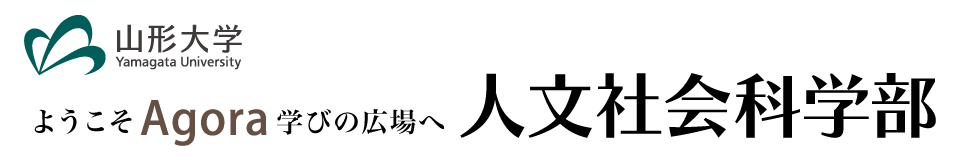


ホーム > 人文社会科学部附属研究所 > やまがた地域社会研究所:安達峰一郎研究資料室 > 資料室ブログ > 1900年パリ万博前後の安達夫妻(その2)―岡村司『西遊日誌』と『安井てつ書簡集』から―
このブログは、高校生・大学生、一般の方に、外交官・常設国際司法裁判所裁判官として活躍した安達峰一郎の「国際法にもとづく平和と正義」の精神を広く知って頂くために設けました。安達峰一郎に関するイベント等の情報、安達峰一郎の人となりや業績等に関わる資料紹介、コラムやエッセイ、今日の国際関係に関わる記事等を随時配信していきます。
投稿日:2019年6月10日
4、和歌と漢詩
「かね子」夫人と「安井て津子」について、安井の書簡は、「内心は」「共に日本の女子」と語っている。「共に日本の女子」というのは、どのような点にあるのだろうか。二人の共通点として、和歌があったのでは、というのが今回の話である。
鏡子夫人が数多くの和歌を残していることはよく知られていることといえよう。例えば、昭和一三年の『歌集 二春と一と夏 遠き子らへと』や昭和一六年の『歌集 過きし一と影 遠き子らへ』は安達鏡子の名前で印刷・発行された歌集であり、さらに日本に帰って財団を作った最初の仕事として『夫 安達峰一郎』という歌の本を出版しているからである。いずれも峰一郎が亡くなった後のものであるが、若い頃から歌いためてきたものをまとめたものと言うことができる。
これに対し、安井が歌を蓄えていた、という話はあまり知られていないかもしれない。ただ、安井が樋口一葉に教えを受けていたということは、その伝記でも触れられていることである。そして、調べてみると、その人脈は広く、本格的に文学作品に親しんでいたようであり、興味深いものがある。
樋口一葉の日記には、安井のことが何度か出てくるという。それによると、安井が持ってきたリンゴを一緒に食べたとの話が出ており(『安井てつ伝』36頁)、そのリンゴは、あるいは安井と親交があった羽仁もと子が岩手から送ったものかもしれない、とされている。そして、この羽仁もと子と明治女学校の同窓だったのが、木下杢太郎の姉にあたる太田竹子であり、竹子は、先に触れた山形出身の裁判官斎藤十一郎の妻となった人物である。何よりも一葉と竹子は親しく、二人で撮影した女学生風の写真が木下杢太郎記念館にある、という。一葉の日記には、斎藤との結婚後の1893年(明治26年)4月29日に「太田竹子君、斎藤それがしの妻に成らる。それも来る。西片町に住居するよし。我が家をも訪はんなどいふ」(『一葉全集第三卷』316頁)と記されている。
安井が一葉を訪ねることができなくなったのは、英国留学が決まったからである。一葉の日記にも「安井君は、海外留学の出発期日迫れるに、語学専門にならはるゝ頃とて、此日頃打たえられしなり」(『一葉全集第四巻』286頁。明治29年(1896年)7月13日)とある。安井が代わって訪ねるようになったのは(正確には「数ヶ月間津田梅子先生の御宅において頂き、此処から学校[東京女子師範学校小学校第二部]に通勤」(『安井てつ伝』39頁)したという)、津田梅子であり、こうして見ると、留学先で知り合った新渡戸稲造を加え、五千円札のデザインに採用された三人(新渡戸稲造・樋口一葉・津田梅子)と、安井はつき合いがあった、ということになる。
このことは、夫人と「安井て津子」が和歌で繋がっていると言うよりも、むしろ当時の女性の教養として和歌をともに学んでいたということにすぎないというだけなのかもしれない。安井については、イギリス留学に向かう船旅の最中に和歌を作って友人に送ったりしたが(『若き日のあと』37頁以下)、留学中はむしろ英語の詩を作ったりしており(同88頁以下)、現地に溶け込もうと努力している様子がうかがえる。これに対して、鏡子夫人は、峰一郎の傍に寄り添いながら和歌を作り続けた。同じ日本人女性であったが、海外生活が長かった夫人は、日本に対する郷愁を抱きながら、だからこそ日本人女性としての教養である和歌を続けたのかもしれない。
日本女性が和歌とすれば、この時代の男性の教養は漢詩だった。若き峰一郎が、自身が学んだ学校の校長(米沢出身の齋藤篤信)に 送った漢詩が書簡集25頁にも収録されているように、当時の修練として漢詩がその教養を表していたと言える。
岡村もまた、漢詩を能くしていたようである。司法省法学校に入学する前に、三島毅(中洲)が経営する二松学舎に入学している。この学校は、漢文塾とされており、三島がかつて司法省の官吏をしており、ボアソナードとも親交があった人物であり、その繋がりも見越しての入学だったのかもしれない。いずれにせよ、漢詩を能くしていたことは、残された資料からもうかがえる。
もっとも、安達や岡村の漢詩は、このように、受験科目と繋がっていたことも指摘しておかなければならない。司法省法学校の入学試験は、白文を読み下すこととされており(安達の書簡では「四書五経ノ弁書及ビ支那日本高等ノ歴史等」(書簡集27頁)とされている)、いわば外国語としての漢文の知識が試されたことになる。当時の知識人の外国語通は、漢文・漢詩に精通していたことがその基礎にあったと見ることもできよう。
また、漢文については、素読というのがある。幼い頃から声を出して漢文・漢詩を読み上げるという勉強方法は、案外、語学学習一般に通じることだったのかもしれない。和歌もまた、歌いあげる、と言う。安達や岡村、鏡子夫人や安井、といった当時の知識人たちの共通した素養と語学の才能とが関係していたと考えると、パリの街を自由に歩き回る彼らの姿の基礎を見た、と言う思いにかられるところである。
月別アーカイブ
年別アーカイブ
サイトマップを閉じる ▲