

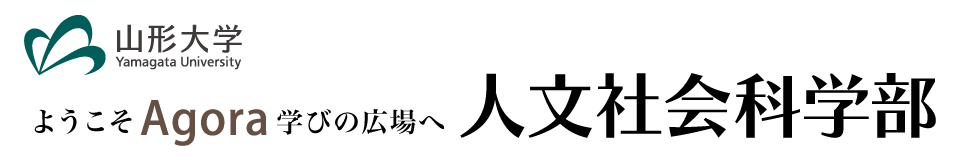


ホーム > 人文社会科学部附属研究所 > やまがた地域社会研究所:安達峰一郎研究資料室 > 資料室ブログ > 1900年パリ万博前後の安達夫妻(その2)―岡村司『西遊日誌』と『安井てつ書簡集』から―
このブログは、高校生・大学生、一般の方に、外交官・常設国際司法裁判所裁判官として活躍した安達峰一郎の「国際法にもとづく平和と正義」の精神を広く知って頂くために設けました。安達峰一郎に関するイベント等の情報、安達峰一郎の人となりや業績等に関わる資料紹介、コラムやエッセイ、今日の国際関係に関わる記事等を随時配信していきます。
投稿日:2019年6月17日
6、キリスト教
岡村の日誌には新渡戸稲造のことは出てこない。岡村と安井とは安井がパリに出てきてからは、ほぼ毎日会っており、その様子は詳しく載っているのだが、パリ万博の審査員としてフランス政府の招聘でパリに居たはずの新渡戸の名前は出てこないのである。後に京都帝国大学で同僚になるとはいえ、この時、岡村と新渡戸との間には接点がなかった、と言ってよかろう。
これに対して、安達と新渡戸との間はどうだったか。峰一郎の弟が新渡戸の教えを受けていたようであり、あるいはすでに個人的ななんらかの繋がりがあったかもしれない。さらには、パリ万博の審査員(新渡戸)と、万博準備のために日本政府からパリに派遣された外交官(安達)との関係であり、この時期には様々な機会に語り合える機会はあったと思われる。後に、国際連盟においてこの2人が重要な役割を演じることとなる、ということは良く知られたことであり、その協力関係がこの時期の体験と結びついていたならば、面白い調査対象となるのであるが、よくわからない。
また、新渡戸がどのような経緯でパリ万博の審査員となったかについては、(その研究はあるのだろうが)、残念ながら知識がない。ただ、直前に出版された『武士道』がすでにベストセラーとなっていたことが大きな理由だったのかもしれない。そして、もう1つ、彼がキリスト教徒であったことが関係していたのではないか、と私には思えるのだが、どうであろうか。というのは、次のような理由からである。
岡村の日誌には、岡村がキリスト教に興味を持ち、教会を訪れるくだりがある。その直前に「センジョセフ病院」を見学し(10日)、キリスト教を基盤とした慈善事業のあり方に感心したからである。しかし、彼は、その後、次のように述べ、キリスト教に対し、いわば愛想を尽かしている。
「[明治33年(1900年)4月15日]日曜日。朝、センシュルピース寺院に至り、一人の教僧に面会して、耶蘇教の教義、儀式等の事を質問しけり。然るに其の答ふる所は誠に馬鹿らしく、
神は唯一あるのみ、やみくもに之を信ずるこそよけれ、善を為せば極楽に行き、悪を為せば地獄に落つること、神の賞罰なり。洗礼を受けて身の汚れを払ひて、始めて真の人間となるなり。[中略]
愚にもつかぬ事のみ言ひおりて、人間はかくも迷ひに陥り、道理がわからなくなるものにやと呆れ返り候。[中略、日本人は]皇祖皇宗よりの遺訓を守り、誠の心に従って身を修め行くものから、別に神に祷[いの]ることもなしと云ひけるに、彼の僧、されば日本人は神を信ぜぬよな文明人とは言はれじなどと澹言[たわごと]をぬかしけり。」
ただ信ぜよという教義には、信仰についての真理も含まれているとは思うものの、キリスト教徒でなければ文明人ではないという排除の論理には、私も、岡村ととともに怒りにも似た感情を抱くところではある。だが、そのことはそのこととして、この当時の西洋人が日本人を見る目にはこのような排除の論理が隠されていたことは知っておいて良い。また、このことから、少なくとも新渡戸は、キリスト教徒となったことにより、西洋人からは認められる資格を得ていた、ということになる。
ちなみに、安井は、洗礼こそ受けていなかったが、すでにパリ万博において新渡戸と会う前に、キリスト教に近づいていた。キリスト教について、岡村と次のような会話があったという。
「て津子が頗るキリスト教に傾けるようになりたる経緯を聞きぬ。その訳は人間は到底欠点あるを免れず、これを師としても決して完全の人となるべからず。それよりはここに完全無欠なる神というものあることを信じ、これを仰ぎ、これに倣いて完全の人とならんには如かじと想いたるに由れり。と云えり。さればてつ子が、キリスト教に傾けりと云うは、世間の者が神を信じ、ただその冥福を求めるが如きとは大いにその趣を異にし、深く咎むるに及ばざるべし」
この日誌の日付は、明治33年(1900年)5月14日の月曜日となっている。安井はこの翌日、パリを離れいったんロンドンに戻りそこから新渡戸の妻のいるアメリカを経由して帰国の途についている。そして、安井がキリスト教の洗礼を受けたのは、日本に帰ってしばらくしてのことになる。
安井がどのようにしてキリスト教を受け入れたのかということは、岡村の言葉を通じてのことであるから、これだけではわからない。この説明には、岡村らしい理解も垣間見えるからである。しかし、このことは別の機会に論じることとしたい。
さて、一見すると安達とは全く関係のない話を続けてきた。しかし、岡村のキリスト教に対する日誌の記述を読みながら、私の心に浮かんだのは安達のことである。安達がキリスト教をどのように考えていたのか聞く機会はないのだが、安達が活躍した当時の西欧社会は、キリスト教徒ではない人々は野蛮人だ、文明人ではない、という偏見がまだまだ生きていた社会であった。そのような西欧社会において、「世界の良心」と評されるまで、安達はどのような努力をしたのであろうか。そのことを考えたのである。
学者である岡村は、西欧の良いところを取り、悪いところを捨てることができたであろう。しかし、外交官や常設国際司法裁判所で裁判官を務めた安達は西欧社会と丸ごと向き合う必要があったはずである。例えば、先に触れたように、パリ万博においても、日本の待遇は決して良いものではなかったようである。岡村は、日本館が植民地のエリアに設けられたり、見世物的な扱いで日本女性が扱われたりしていたことに対して、その日誌の中で非難を繰り返している。したがって、安達に対してもそのことは伝えたと思われる。しかし、安達個人に対する非難は一行も書かれていない。安達が同じ思いだったかはわからないが、フランス政府と日本政府との間でギリギリの調整を行なってきたことを岡村も分かっていたのではあるまいか。そして、その苦労も知っていたのではなかろうか。
月別アーカイブ
年別アーカイブ
サイトマップを閉じる ▲