

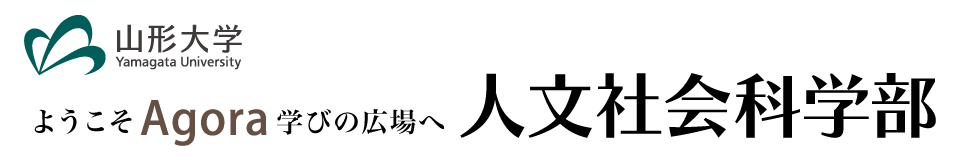


ホーム > 研究所 > やまがた地域社会研究所:安達峰一郎研究資料室 > 資料室ブログ
このブログは、高校生・大学生、一般の方に、外交官・常設国際司法裁判所裁判官として活躍した安達峰一郎の「国際法にもとづく平和と正義」の精神を広く知って頂くために設けました。安達峰一郎に関するイベント等の情報、安達峰一郎の人となりや業績等に関わる資料紹介、コラムやエッセイ、今日の国際関係に関わる記事等を随時配信していきます。
投稿日:2018年12月17日
3、パリでの交遊く
岡村が出会い、安達とも関係する日本人で注目されるのは、大審院判事の河村善益と清水一郎の二人がまず挙げられる。23日の日記には「此の二氏は司法制度視察の為め来りたるものにて、来月末に帰朝すとの事なり。」という。両名とも司法省法学校正則科二期生で、梅謙次郎や後述の小宮三保松らと同窓であった(ただし、清水は改名前の名を坪根直吉といい、同校は中退とされる。手塚豊『手塚豊著作集第9巻明治法学教育史の研究』(1988・慶応通信)81頁)。ちなみに、その翌日24日には、岡村、勝本とともに、安達の招飲を受け(河村は腹痛のため欠席)、安達の家族と一緒に食事をしている。パリ到着早々の歓待であり、その様子については(その2)で触れることとしたい。
岡村を26日の夜に訪ねて来たのが、池辺義象。第一高等中学校で夏目漱石を教えた国文学者・法制史学者であり、安達や岡村も習ったかどうかは今後の調査課題だが、帰国後京都帝国大学で岡村と同僚となる人物である(山本順二『漱石のパリ日記』20頁)。彼と岡村は、安達や栗野の要請もあり、パリ通信社のためにフランスの通信を日本の新聞に送付し、また逆に日本の情報をパリの新聞に投稿することを請け負っている。今で言うアルバイトである。
翌27日、公使館で安達とともにいたのが、大蔵省橋本圭三郎(明治23年(1890年)東京帝大法科大学政治学科卒。同年7月11日官報127頁参照)で、岡村は一緒に博覧会場の築造を見物したという。
11月3日は明治天皇の誕生日で天長節。公使館で夜会。「会する者五十人計り」。ここには、その後東京帝大で社会学講座を担当する建部遯吾や、商法の編纂にも参画した長森敬斐の養子で同じく帝国大学卒の東京地裁検事正長森藤吉郎も居合わせたと言う。長森は、河村、清水とともに欧米視察中であった。
7日には、「安達氏より今夕招宴に高根義人氏を同伴すべしとの葉書ありたれども、高根氏の宿所を知らざるを以て同伴することを得ざりき」との記述が見える。高根義人とは、織田万とともに京都帝大設立のために留学した商法学者であり(潮木守一『京都帝国大学の挑戦』参照)、岡村とは同僚となる。なお、この晩の「来客は長森藤吉郎、橋本圭三郎、佐々木某、池辺義象、人見一太郎、橋本氏及余の七人なりき」と言う(人見はジャーナリスト。『欧州見聞録』(1901)がある)。
8日は、栗野公使の招宴で「来客は河村善益、清水一郎、長森藤吉郎、池辺義象及余の五人なりき、余は皆公使館員なり。伊東大佐及佐藤書記官[佐藤愛麿公使館一等書記官]に面会しぬ」とある。
また、11日「夜兼て安達氏より招請を受けたるオペラコミックの見物に赴きぬ」「一人前十五フラン計りなりと云ふ。安達氏夫妻、橋本圭三郎、佐々木某、勝本勘三郎氏及余の六人なりき。安達氏の御馳走なり」。
さらに17日には「午下、河村善益、清水一郎、長森藤吉郎、勝本勘三郎及清水澄諸氏と同じく未決監及裁判所を一見しぬ」と言う。
清水澄は、安達の二学年下で明治27年7月帝国大学法科大学仏蘭西法撰修卒業(明治27年(1894年)7月11日官報128頁参照)。憲法・行政法学者であり、学習院大学教授、慶應大学教授を歴任した。最後の枢密院議長としても有名である。
先に出てきた高根義人とこの清水澄は、この後しばらくして本来の滞在先であるベルリンに帰ることになる。
また、12月2日には、河村善益と清水一郎、さらに長森藤吉郎もロンドンに向けて出発している。
投稿日:2018年11月29日
2、岡村司・パリに着く
まずは、岡村の日誌から、峰一郎と岡村との交流を抜き出してみよう。
明治32年(1899年)10月19日、岡村は、マルセイユに到着する。領事館員とされる谷口氏(実際はかなり怪しい人物との評は箕作元八の日記に見える)が出迎えている。岡村は、この段階で峰一郎から、パリ到着の日時を電報にて通知ありたしとの連絡を(谷口氏を通じての連絡かどうかははっきりしないが)受けている。マルセイユは開港2500年の記念祭開催中であったが、その見物は早々に切り上げ、翌日夕方7時40分発の急行列車で出発することを同行者と協議し、20日「安達氏には明朝九時巴里[パリ]着を電報」した、という。同行者とは、箕作元八、村上直三郎、坂本陸軍歩兵中佐、の他、勝本勘三郎、高安右人、村上安蔵であり、岡村と勝本、高安、村上の四人は、この日、パリに向かうこととなったわけである。
このうち、マルセイユで別れた箕作元八は、フランス革命史などを専門とした西洋史学者であり、この当時第一高等中学校教授。後に東京帝大教授となっている。この時はパリには行かず、スイス経由でベルリンに向かうが、後に岡村と入れ替わりにパリで留学生活を送った人物である[前註1参照]。
村上直三郎と坂本陸軍歩兵中佐は、ともにイタリア・ローマに赴くはずとされ、特に後者はイタリア公使館付の武官としての赴任であったようである。
これに対して、岡村とパリに同行した勝本勘三郎は、安達と同様、司法省法学校以来の同窓生であった(但し、卒業は一年後のようである。明治26年(1893年)7月11日官報第3009号111頁)。岡村と同様、京都帝国大学の助教授としての留学である。
高安右人と村上安蔵は医者で、前者は帝大医学部卒の眼科医、後に第四高等中学校に開設された医学部の教授に就任しており、後者も長崎の第五高等学校医学部主事[現在の学部長]となった人物であり、両者はパリを経て、ベルリンに向かうこととなる。
翌日、パリのリヨン駅では四人を峰一郎が出迎えている。馬車で日本公使館近方の旅館に荷物を置いたのち、公使館で公使の栗野慎一郎と面談し、「安達氏に導かれ」下宿探しを早々にはじめている。直前まで留学していた同級生の織田万の下宿先が空いていなかったこともあり、別の安価な下宿先に明後日から移ることとなった。岡村は、翌日も安達と食事をし、天長節の夜会に招待されるが、そのためには燕尾服がなければならないとの忠告を得て、その注文をすることにしたという。
つまり、何から何まで安達が世話をしているわけである。
ちなみに、岡村はこの日(21日)、梅謙次郎の旧師ジョルジュ・アッペールを訪ねており、その様子もまた興味深いのだが、そういった細々した話は省略することとし、以下では、安達の下にどのような人々が集っていたか、に焦点を絞ることにしよう。
投稿日:2018年11月26日
1、はじめに
安達峰一郎の司法省法学校からの同級生に、民法学者の岡村司がいる。岡村は、イエ制度批判などの業績で注目された著名な学者であるが、比較的若くして亡くなったことや、彼亡き後の民法研究が方法論的にも大きく変化していったことなどから、今ではいわば忘れられた民法学者となってしまった感がある。しかし、ボアソナードの最後の教え子とでもいった民法学者でもあり、ボアソナード民法典の研究者たる私としては、安達とともに興味を持つ対象である。
その岡村が残した日記がある。司法省法学校入学直前の明治18年(1885年)から亡くなった大正11年(1922年)までのもので、とりわけ明治32年(1899年)から同34年(1901年)までの『西遊日誌』は、ヨーロッパ留学時の日記で、妻や家族宛の書簡も兼ねていたようで詳細なものとなっている[註1]。安達にこの種の日記があれば面白いのだが、赴任先では夫婦で過ごすことが多かったようで、わざわざ日記を認めて日々の様子を夫人に伝える必要はなかったということもできよう。他方、岡村の日記を読むとパリにおける安達峰一郎の様子が詳しく記されており、両者の交流を日ごとに読み取ることができる[註2]。そこで、1900年前後における安達の様子を、この日記から読み解いてみることにした。
ところで、その過程で、興味深い人物に出会うこととなった。それは、岡村を「従兄」(いとこ)と呼ぶ、安井てつ、である。安井は、岡村の日記では「安井て津子」と記されているが、「安井哲」の表記も用いた人物であり、新渡戸稲造の後を継いで後の東京女子大の2代目学長に就任した女性教育者として名高い人であり、岡村に先立つ明治30年(1897年)からイギリスに留学していた。そして、その帰国前の最後の期間、万国博覧会を見学するためにパリを訪ねており、その前後の様子が友人への書簡 [註3] に伝えられている。実は、安井は高等師範学校女子師範学科卒業の一期生であり[註4]、安達の妻となった高澤鏡(呼び名は「かね」で「鏡子」とも表記される)[註5]の一つ先輩にあたり、鏡子夫人の話も書簡には出てくる。つまり、岡村司の『西遊日誌』と『安井てつ書簡集』をつなげていくと、二人の目から見たこの時期における安達峰一郎・鏡子夫妻の様子を浮き彫りにすることができことになる。夫妻と岡村・安井との交流については、これまであまり知られていないと思われるので、岡村司と安井てつの人柄を紹介しながら、二人から見た安達夫妻像を探ることとした。
もっとも、このブログでは、まず、岡村の日記をもとに当時のパリ日本人社交界を管見したい(その1)。なぜなら、この時期のパリは、まだ開催前である万国博覧会一色であり、これを目当ての日本人も数多く訪れているからである。1900年パリ万博のテーマは「過去を振り返り20世紀を展望する」であったといわれるが、むしろ20世紀の幕開けを祝う国際博覧会であった。きらやかに着飾った婦人を伴った紳士がシルクハットにステッキを持ち、歩く歩道で移動するような華やかな映像も残されている。安達は、このパリ万博を日本としてサポートするためにパリに赴任している。そこで、安達夫妻の様子を語る前に、この時期のパリの雰囲気を紹介することとしたいからである。
そのうえで、日をおいて「(その2)」として、安井がパリを訪れた1900(明治33)年5月を中心に、パリ万博周辺での安達夫妻の様子を描写したい。こちらがメインであるが、安達夫妻との接点から見える岡村司と安井てつについても紹介していくこととしよう。
註1 この当時、妻や子供と別れての単身留学においては詳細な日記を認め、これをやりとりした風習があったのかもしれない。例えば、岡村と留学先までの船旅をともにした箕作元八には滞欧日記が存在し、解説が付され公刊されている。井手文子・柴田三千雄編集・解説『箕作元八・滞欧「箙梅日記」』(1984)。箕作の留学は二度目のことで、一度目の際には日記は存在していないようなので、この日記は妻子宛てのものであったと考えられる。また、岡村から10年以上後のものではあるが、同じく民法の家族法分野の研究者として有名な穂積重遠(穂積陳重の息子で後に東大教授)も同様の日記を残している。穂積重行『欧米留学日記(1912〜1916年) 大正一法学者の出発』(1988・岩波書店)
註2 鈴木良・福井純子「史料紹介「岡村司『西遊日誌』(その一)」『立命館産業社会論集』1995年3月第30巻第4号(通巻83号)109頁以下、同「(その二)」同31巻第1号167頁以下、同「(その三)」同第2号127頁以下、同「(その四)」同3号183頁以下。
註3 青山なを『若き日のあと―――安井てつ書簡集』(1965・安井先生歿後二十年記念出版刊行会)
註4 明治23年(1890年)四月七日官報第2027号76頁参照。「女子師範学科卒業生」「安井てつ 東京府士族」として掲載されている。
註5 明治24年(1891年)三月二七日官報2319号290頁参照。同じく「女子師範学科卒業生」「高澤鏡 山形縣士族」として掲載されている。
投稿日:2018年10月23日
10月22日(月)、グローバル・プロブレマティーク基礎演習dの授業において、山辺町安達峰一郎博士顕彰会理事の佐藤継雄先生に、「世界平和のため活躍した安達峰一郎博士」というテーマでお話をしていただきました。佐藤継雄先生は、顕彰会が2011年に発行した安達峰一郎書簡集の編者の一人でもあり、特に安達の幼少期から学生時代について研究されてきた方です。
講義では、法学を志した動機として山形での自由民権運動や関山新道事件があったのではないかということ、そして法学の中でも国際法を専攻した動機として当時の不平等条約の改正という日本外交の課題(その象徴としてのノルマントン号事件)やイタリア人国際法学者パテルノストロによる国際法講義の通訳をしていたことなどについて、様々な資料を使いながら丁寧に説明していただきました。若き安達峰一郎が法学を志して上京するまでの努力や苦労を聴いた学生は、語学の習得だけでなく自分の核となる専門性をもつことの重要さを学びとったようです。
なお、この授業ではグローバルスタディーズ・コースの2年生が、今後半期にわたって安達峰一郎の功績を日本外交、国際連盟、国際裁判という3つの観点から検討していきます。

投稿日:2018年10月19日
ウィルソン外交は、1901年から1909年迄2期大統領であったセオドア・ルーズベルトの「棍棒外交」と言われるような実力本位の外交とは異なって「宣教師外交」と言われています。ウィルソンは宣教師であったことはないようですが、メキシコをはじめとした中米諸国への介入は「立憲政治を相手国に承知させようとする一種の宗教的義務感をともなっていた」とされています。(長沼秀世『ウィルソン』、山川出版社、2013年、49頁)。
この「宣教師外交」の帰結はどうだったか。補足としてウエルタ政府倒壊後の結末も見ておきましょう。
1914年夏には第一次世界大戦が勃発していますから、ウィルソンはイギリスと関係の深いメキシコとの関係悪化を避けるため、ウエルタ政府倒壊後は干渉を抑制します。しかし、メキシコではビリャ派、サパタ派とカランサ派の内戦が続きます。アメリカでもウィルソン批判が高まり、ウィルソンは1915年6月に「平和勧告」を行います。この和平提案が受け入れられなければ、アメリカが介入するという脅し文句が付け加えられ、安達が帰国の途につく8月にはカランス派が勝利します。
このウィルソンの勧告は、アメリカ国内からの批判、とくに「棍棒外交」で知られるセオドア・ルーズベルトのウィルソン批判を背景にして行われたようです。安達は、ルーズベルトが、このままではモンロー主義(欧州諸国がアメリカ大陸に干渉することを排除するかわりに、アメリカも欧州には干渉しないとする外交ドクトリン)を抛てるか(欧州諸国の介入を招くからという理由でしょう)、そうでなければ、かつて自らがキューバに対して行った(1906年にアメリカはキューバを占領下に置きました)のと同様にメキシコにも武力干渉を行い、アメリカ大陸における覇者としての米国の権威を世界に示すべきだと主張していることに触れています(加藤高明外相宛、1915年6月22日付け)。
以上長くなりましたが、駐メキシコ公使時代の安達に関係する出来事の大筋を辿ってきました。メキシコでは1917年にカランサ政権のもとで当時最も民主主義的と言われた憲法が制定され、安達が予想したようにアメリカの「なぶり殺しになる」ということはなかったようです。しかし、革命動乱の渦中にあった安達は、立憲政治を確立するというそれ自体は批判の余地がない正当な理想であっても、高邁な理念を振りかざして、実情を無視した干渉がメキシコの革命動乱の泥沼化をもたらした一因と見ていたように思われます。
なるほどウィルソンの「宣教師外交」はセオドア・ルーズベルトの「棍棒外交」とは対極のように思われます。しかし、安達が寺内正毅宛書簡でウィルソンの「大驕挙」と書いたとき、このメキシコ革命動乱時におけるウィルソンの「宣教師外交」がはらむある種の危険性が脳裏にあったのではないでしょうか。上部シレジアにおけるドイツ少数民族問題の解決に見られるような国際連盟日本代表時代における安達の行動スタイル、国際法にもとづいて紛争を当事者の言い分を粘り強く聞きながら解決していくという安達の外交スタイルは、このような経験も積んで磨かれていったのではないでしょうか。
月別アーカイブ
年別アーカイブ
サイトマップを閉じる ▲