

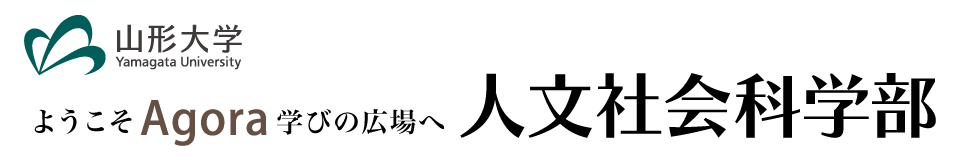


ホーム > 研究所 > やまがた地域社会研究所:安達峰一郎研究資料室 > 資料室ブログ
このブログは、高校生・大学生、一般の方に、外交官・常設国際司法裁判所裁判官として活躍した安達峰一郎の「国際法にもとづく平和と正義」の精神を広く知って頂くために設けました。安達峰一郎に関するイベント等の情報、安達峰一郎の人となりや業績等に関わる資料紹介、コラムやエッセイ、今日の国際関係に関わる記事等を随時配信していきます。
投稿日:2019年6月17日
6、キリスト教
岡村の日誌には新渡戸稲造のことは出てこない。岡村と安井とは安井がパリに出てきてからは、ほぼ毎日会っており、その様子は詳しく載っているのだが、パリ万博の審査員としてフランス政府の招聘でパリに居たはずの新渡戸の名前は出てこないのである。後に京都帝国大学で同僚になるとはいえ、この時、岡村と新渡戸との間には接点がなかった、と言ってよかろう。
これに対して、安達と新渡戸との間はどうだったか。峰一郎の弟が新渡戸の教えを受けていたようであり、あるいはすでに個人的ななんらかの繋がりがあったかもしれない。さらには、パリ万博の審査員(新渡戸)と、万博準備のために日本政府からパリに派遣された外交官(安達)との関係であり、この時期には様々な機会に語り合える機会はあったと思われる。後に、国際連盟においてこの2人が重要な役割を演じることとなる、ということは良く知られたことであり、その協力関係がこの時期の体験と結びついていたならば、面白い調査対象となるのであるが、よくわからない。
また、新渡戸がどのような経緯でパリ万博の審査員となったかについては、(その研究はあるのだろうが)、残念ながら知識がない。ただ、直前に出版された『武士道』がすでにベストセラーとなっていたことが大きな理由だったのかもしれない。そして、もう1つ、彼がキリスト教徒であったことが関係していたのではないか、と私には思えるのだが、どうであろうか。というのは、次のような理由からである。
岡村の日誌には、岡村がキリスト教に興味を持ち、教会を訪れるくだりがある。その直前に「センジョセフ病院」を見学し(10日)、キリスト教を基盤とした慈善事業のあり方に感心したからである。しかし、彼は、その後、次のように述べ、キリスト教に対し、いわば愛想を尽かしている。
「[明治33年(1900年)4月15日]日曜日。朝、センシュルピース寺院に至り、一人の教僧に面会して、耶蘇教の教義、儀式等の事を質問しけり。然るに其の答ふる所は誠に馬鹿らしく、
神は唯一あるのみ、やみくもに之を信ずるこそよけれ、善を為せば極楽に行き、悪を為せば地獄に落つること、神の賞罰なり。洗礼を受けて身の汚れを払ひて、始めて真の人間となるなり。[中略]
愚にもつかぬ事のみ言ひおりて、人間はかくも迷ひに陥り、道理がわからなくなるものにやと呆れ返り候。[中略、日本人は]皇祖皇宗よりの遺訓を守り、誠の心に従って身を修め行くものから、別に神に祷[いの]ることもなしと云ひけるに、彼の僧、されば日本人は神を信ぜぬよな文明人とは言はれじなどと澹言[たわごと]をぬかしけり。」
ただ信ぜよという教義には、信仰についての真理も含まれているとは思うものの、キリスト教徒でなければ文明人ではないという排除の論理には、私も、岡村ととともに怒りにも似た感情を抱くところではある。だが、そのことはそのこととして、この当時の西洋人が日本人を見る目にはこのような排除の論理が隠されていたことは知っておいて良い。また、このことから、少なくとも新渡戸は、キリスト教徒となったことにより、西洋人からは認められる資格を得ていた、ということになる。
ちなみに、安井は、洗礼こそ受けていなかったが、すでにパリ万博において新渡戸と会う前に、キリスト教に近づいていた。キリスト教について、岡村と次のような会話があったという。
「て津子が頗るキリスト教に傾けるようになりたる経緯を聞きぬ。その訳は人間は到底欠点あるを免れず、これを師としても決して完全の人となるべからず。それよりはここに完全無欠なる神というものあることを信じ、これを仰ぎ、これに倣いて完全の人とならんには如かじと想いたるに由れり。と云えり。さればてつ子が、キリスト教に傾けりと云うは、世間の者が神を信じ、ただその冥福を求めるが如きとは大いにその趣を異にし、深く咎むるに及ばざるべし」
この日誌の日付は、明治33年(1900年)5月14日の月曜日となっている。安井はこの翌日、パリを離れいったんロンドンに戻りそこから新渡戸の妻のいるアメリカを経由して帰国の途についている。そして、安井がキリスト教の洗礼を受けたのは、日本に帰ってしばらくしてのことになる。
安井がどのようにしてキリスト教を受け入れたのかということは、岡村の言葉を通じてのことであるから、これだけではわからない。この説明には、岡村らしい理解も垣間見えるからである。しかし、このことは別の機会に論じることとしたい。
さて、一見すると安達とは全く関係のない話を続けてきた。しかし、岡村のキリスト教に対する日誌の記述を読みながら、私の心に浮かんだのは安達のことである。安達がキリスト教をどのように考えていたのか聞く機会はないのだが、安達が活躍した当時の西欧社会は、キリスト教徒ではない人々は野蛮人だ、文明人ではない、という偏見がまだまだ生きていた社会であった。そのような西欧社会において、「世界の良心」と評されるまで、安達はどのような努力をしたのであろうか。そのことを考えたのである。
学者である岡村は、西欧の良いところを取り、悪いところを捨てることができたであろう。しかし、外交官や常設国際司法裁判所で裁判官を務めた安達は西欧社会と丸ごと向き合う必要があったはずである。例えば、先に触れたように、パリ万博においても、日本の待遇は決して良いものではなかったようである。岡村は、日本館が植民地のエリアに設けられたり、見世物的な扱いで日本女性が扱われたりしていたことに対して、その日誌の中で非難を繰り返している。したがって、安達に対してもそのことは伝えたと思われる。しかし、安達個人に対する非難は一行も書かれていない。安達が同じ思いだったかはわからないが、フランス政府と日本政府との間でギリギリの調整を行なってきたことを岡村も分かっていたのではあるまいか。そして、その苦労も知っていたのではなかろうか。
投稿日:2019年6月17日
5、万博見物
「安井て津子」がパリに来たのは、1900年(明治33年)5月1日のことであった。それから15日にロンドンに還るまでの安達夫妻と岡村司・安井てつとの交流を辿ってみたい。この期間中の日誌には集中的にパリ万博の様子が綴られているからである。
5月1日
「安井て津子の書あり。曰く、一日夕刻、巴里に着すべし、宿所は安達氏の周旋によりて、日本公使館の近傍なるリュードラポンプに定めたりと。」
2日
「晴、朝、リュードラポンプ町に至りて安井て津子を訪ひぬ。此の家の主婦は六十歳計りなるアイルランド人にして能く英語を操り、懇切に世話をし呉るゝと云へり」
この日の文面からは、安達夫妻の斡旋により宿での生活を始めた安井の姿が浮かんでくる。英語に堪能な家主の下で、安井は岡村に留学の成果を伝えている。その内容は3点ある。短く引用すると、
1、「日本女子教育の振るわざるは男子の女子に期待する所のものゝ極めて卑汚なるに在りと。」
2、「女子教育の目的は完全なる女人を養成するに在り、」
3、「英国女子の地位の高尚にして、自由に言論するの風を喜ぶものゝ如し。」
また、フランス人とイギリス人とを比較しているのが面白い。
「仏国人は開轄[快活の意味か]なれども軽躁なり。英国人は沈鬱なれども着実なり。余は寧ろ英国人を可となすなど云へりき。」
これらの言動に対する岡村の評価は次のようなものであった。
「其の言の得失は姑く舎き[しばらくおき]、是れ皆留学の結果にして一段の見識を長ぜるものと評すべきなり。」
この後、安井は鏡子夫人と一緒に博覧会の見物に出かけている。
「[昼食をご馳走になった後]やがて安達氏の細君来りて安井と同じく博覧会の見物に赴けり。余は公使館に行きて安達峯一郎氏を見き。」
次いで、4日には、安達夫妻、息子の太郎とともに、安井が岡村のもとを訪ねてきている。食事をともにし、公園を散歩し、ブローニュの森まで来て別れたという。
4日
「晴、午時、安達峯一郎氏、其の細君鏡子、其の幼児太郎及び安井て津子と共に来けり。宿のおかみさんに頼みて午餐を調理し建部氏を併せて六人、食卓を囲みて午餐を喫しぬ。之より相伴ふて公園に散歩し、其の帰りを送りてブローニュに至りて別れぬ。」
翌日の5日は、パリ万博の日本館の開館式があった。その様子を伝える岡村が、日本館のあり方に対して不満を述べていることも興味深い。
5日
「晴、午下、万国博覧会内なる日本陳列館の開館式に赴きぬ。日本陳列館はセーヌ河の右岸、トロカデローと云ふ所に在り。トロカデローと云ふ所は外国植民地、例へば英領印度、露領西比利亜、仏領アルゼリー等の陳列館を設くる所にして各本国の陳列館を設くる場所は別にセーヌ河の左岸に在るなり。然るに堂々たる大日本帝国の陳列館を外国植民地の部に建設し、日本をして恰も他国の領地なるが如きの観粗しむるものは、実に国体を害するの尤も甚だしきものにして、余等の第一に不満とする所なり。」
その後、しばらく日誌には安井のことが出てこない。安井が日誌に再登場するのは、一〇日のことである。岡村とともにセーブルの陶器製造所を訪ねているのだが、この間は、連日鏡子夫人と諸方を見物してきたことがその日誌からうかがえる。もっとも、この当日、鏡子夫人の姿はない。恐らくは公使館で予定されていた皇太子殿下御結婚祝賀会の準備に忙しかったのであろう。そして、この夜会こそが、安井と新渡戸稲造とが初めてあった会合であったと思われる。
10日
「晴、午後、安井て津子来りて建部氏と同じくセーブルの陶器製造所に行きて見物しぬ。[中略]て津子は連日、安達鏡子と諸方を見物せし由なるも、此の日は安達子差支ありて独り出でけるなりとぞ。夜、皇太子殿下御結婚祝賀の夜会に日本公使館に赴きぬ。会する者数十百人、いと盛会なりけり。」
次に安井が岡村の日誌に現れるのが、一二日である。パッシー通りの小学校や織物の製造所を視察した様子がうかがえる。鏡子夫人の姿は見えないが、教育機関を参観していることが興味深く、公使館からの紹介状が役立ったという。安達が便宜を与えたとも考えられよう。
12日
「建部遯吾氏と同じくパッシー街に至り、大槻龍治(法学士にて京都市の助役)、立花銑三郎、渡辺千春諸氏及安井て津子と会し、相共に同街なる尋常小学校を参観しき。これは公使館より此等の諸人に同時に参観の紹介状を与へたるなり。[中略]午後、ゴブレン街に至りてゴブレン織物の製造所を見ぬ。[中略]て津子は愈々十五日朝出発、英国に還ると云へり。」
13日(この日は日曜日)
この日の日誌には取り立てて記載されていることはない。しかし、安井が新渡戸と二度目に会ったのが、この日曜日であった。というのも、安井によると、この時、新渡戸とパリで二度会ったとされているからである。
「不思議の事にて新渡戸稲造氏と巴里[パリ]にてスピリッチョアル、フレンドに相成、わづか二度の會合が二十年以来の胞友のごとく相成候、胞友と申しては少しく失禮、師弟のごとくに候」(『安井てつ書簡集』131頁)
そして、初めて会った際に、次のように言われたという。その言葉は、新渡戸の姿を彷彿とさせるものがある。
「先生[新渡戸]は例のフレンドリーな態度で、「あなたが安井さんですか、英国留学の感想はどんなです、ゆっくり話を聞き度いと思うが、丁度此次の日曜日に四五人の者が集つて語り合ふ事になって居るから来ませんか」という意味の事を語られたのである。」(前田多門・高木八尺編『新渡戸博士追憶集』380頁)
この日曜日が一三日である。そして、「公使館」で初めてあったのは、一〇日と言う事になる。「巴里[パリ]に於て万国博覧会が開かれた時であった。私は三年間の英国留学を終へて将に帰朝の途に就かんとする直前、博物会見物のため巴里に出かけて行った。ある日私は巴里に居る多くの日本人と共に、招待を受けて大使館[公使館の誤り]に行ったが、其処で初めて新渡戸先生にお目に懸つたのである」(追憶集379頁)
そして、その翌日の日誌に安井が出てくる。
14日
「陰雨、暴風の兆しあり。[中略]それより安井て津子の寓に赴き[中略]晩餐の饗を受けゝり。此の間、て津子が頗る耶蘇教に傾ける様になりたる経歴を聞きぬ。[後略]」
したがって、安井と新渡戸が二度会ったその翌日に岡村にキリスト教の話をした、ということになる。この日のやりとりについては、別に語ることとしよう。翌一五日、安井はパリを離れる。
15日
「晴、朝、建部遯吾氏と同じくサンラザル停車場に至りて、安井て津子の倫敦に還るを見送りぬ。安達峯一郎夫婦、て津子を送りて在りたり。」
岡村の日誌での安井のその後の消息については、二度触れられている。引用しておこう。
30日
「陰、朝、安井て津子の書あり。曰く、来月二日亜米利加に向けて出発すと。」
6月22日
「安井て津子より、本月九日紐育[ニューヨーク]に着せりとの報あり。岡田朝太郎氏よりも同様の通知あり。此の二人は同船なるべし。」
アメリカで新渡戸の妻と会った後、安井てつが帰国したのは、1900年(明治33年)7月22日のことであった(「留学生帰朝」『官報第五千百二十三号』四四二頁)。
投稿日:2019年6月10日
4、和歌と漢詩
「かね子」夫人と「安井て津子」について、安井の書簡は、「内心は」「共に日本の女子」と語っている。「共に日本の女子」というのは、どのような点にあるのだろうか。二人の共通点として、和歌があったのでは、というのが今回の話である。
鏡子夫人が数多くの和歌を残していることはよく知られていることといえよう。例えば、昭和一三年の『歌集 二春と一と夏 遠き子らへと』や昭和一六年の『歌集 過きし一と影 遠き子らへ』は安達鏡子の名前で印刷・発行された歌集であり、さらに日本に帰って財団を作った最初の仕事として『夫 安達峰一郎』という歌の本を出版しているからである。いずれも峰一郎が亡くなった後のものであるが、若い頃から歌いためてきたものをまとめたものと言うことができる。
これに対し、安井が歌を蓄えていた、という話はあまり知られていないかもしれない。ただ、安井が樋口一葉に教えを受けていたということは、その伝記でも触れられていることである。そして、調べてみると、その人脈は広く、本格的に文学作品に親しんでいたようであり、興味深いものがある。
樋口一葉の日記には、安井のことが何度か出てくるという。それによると、安井が持ってきたリンゴを一緒に食べたとの話が出ており(『安井てつ伝』36頁)、そのリンゴは、あるいは安井と親交があった羽仁もと子が岩手から送ったものかもしれない、とされている。そして、この羽仁もと子と明治女学校の同窓だったのが、木下杢太郎の姉にあたる太田竹子であり、竹子は、先に触れた山形出身の裁判官斎藤十一郎の妻となった人物である。何よりも一葉と竹子は親しく、二人で撮影した女学生風の写真が木下杢太郎記念館にある、という。一葉の日記には、斎藤との結婚後の1893年(明治26年)4月29日に「太田竹子君、斎藤それがしの妻に成らる。それも来る。西片町に住居するよし。我が家をも訪はんなどいふ」(『一葉全集第三卷』316頁)と記されている。
安井が一葉を訪ねることができなくなったのは、英国留学が決まったからである。一葉の日記にも「安井君は、海外留学の出発期日迫れるに、語学専門にならはるゝ頃とて、此日頃打たえられしなり」(『一葉全集第四巻』286頁。明治29年(1896年)7月13日)とある。安井が代わって訪ねるようになったのは(正確には「数ヶ月間津田梅子先生の御宅において頂き、此処から学校[東京女子師範学校小学校第二部]に通勤」(『安井てつ伝』39頁)したという)、津田梅子であり、こうして見ると、留学先で知り合った新渡戸稲造を加え、五千円札のデザインに採用された三人(新渡戸稲造・樋口一葉・津田梅子)と、安井はつき合いがあった、ということになる。
このことは、夫人と「安井て津子」が和歌で繋がっていると言うよりも、むしろ当時の女性の教養として和歌をともに学んでいたということにすぎないというだけなのかもしれない。安井については、イギリス留学に向かう船旅の最中に和歌を作って友人に送ったりしたが(『若き日のあと』37頁以下)、留学中はむしろ英語の詩を作ったりしており(同88頁以下)、現地に溶け込もうと努力している様子がうかがえる。これに対して、鏡子夫人は、峰一郎の傍に寄り添いながら和歌を作り続けた。同じ日本人女性であったが、海外生活が長かった夫人は、日本に対する郷愁を抱きながら、だからこそ日本人女性としての教養である和歌を続けたのかもしれない。
日本女性が和歌とすれば、この時代の男性の教養は漢詩だった。若き峰一郎が、自身が学んだ学校の校長(米沢出身の齋藤篤信)に 送った漢詩が書簡集25頁にも収録されているように、当時の修練として漢詩がその教養を表していたと言える。
岡村もまた、漢詩を能くしていたようである。司法省法学校に入学する前に、三島毅(中洲)が経営する二松学舎に入学している。この学校は、漢文塾とされており、三島がかつて司法省の官吏をしており、ボアソナードとも親交があった人物であり、その繋がりも見越しての入学だったのかもしれない。いずれにせよ、漢詩を能くしていたことは、残された資料からもうかがえる。
もっとも、安達や岡村の漢詩は、このように、受験科目と繋がっていたことも指摘しておかなければならない。司法省法学校の入学試験は、白文を読み下すこととされており(安達の書簡では「四書五経ノ弁書及ビ支那日本高等ノ歴史等」(書簡集27頁)とされている)、いわば外国語としての漢文の知識が試されたことになる。当時の知識人の外国語通は、漢文・漢詩に精通していたことがその基礎にあったと見ることもできよう。
また、漢文については、素読というのがある。幼い頃から声を出して漢文・漢詩を読み上げるという勉強方法は、案外、語学学習一般に通じることだったのかもしれない。和歌もまた、歌いあげる、と言う。安達や岡村、鏡子夫人や安井、といった当時の知識人たちの共通した素養と語学の才能とが関係していたと考えると、パリの街を自由に歩き回る彼らの姿の基礎を見た、と言う思いにかられるところである。
投稿日:2019年6月10日
3、パリの服装
峰一郎からのアドバイスもあって、岡村がパリに到着してすぐに新しい服を仕立てた、ということをこのブログの最初の方で紹介した。岡村はまた、フランスでは「男女皆綾羅[りょうら・美しい衣服]を着飾りキタナキ衣服を着たるものなし。男子は大抵シルクハット(高礼帽)を被り、フロックコートを着し居れり」と記載している(着いてすぐの頃の1899年(明治32年)10月22日)。今回は、その服装のことについて見てみよう。
前回、「安達氏の細君は平常洋服を着するものと見え、一見仏人の如し」という岡村の日誌に触れた。鏡子夫人は、洋服を着こなしていたことがこの記述からわかるのだが、岡村は、日本人の女性が洋服を着こなすことが出来るということについて、実は、懐疑的であった。こんな記述がある。
「日本公使館天長節の夜会に赴きぬ。会する者五十人計り。皆日本人なり。公使館員の家族の婦人五六人居りたり。皆洋服を着けたれども如何にも似合はず」
(11月3日)
「公使館員の家族の婦人」とされる中に鏡子夫人がいたかどうかは定かではない。しかし、この表現から、岡村は一般的な意見として日本人女性の洋装を「似合わない」と見ていたことが解る。もっとも、そのような日本人女性に対して、鏡子夫人を「一見仏人[フランス人]の如し」と評していることをどう見たらいいだろうか。
鏡子夫人が卒業した高等師範学校高等師範科(現在のお茶の水女子大学)卒業生の写真がそのことを解き明かしてくれるように思われる。同大学のデジタルアーカイブズで見ることができる卒業写真には、当時めずらしかった洋装での写真が掲げられている。つまり、夫人は、日本にいた時から洋服を着ることが何度もあったことが伺えるのである。そして、これは、『安井てつ伝』によると、初代文部大臣の森有礼の欧化政策と関連している、という。つまり、同書は東京女高師の六十年史を引用し「婦人の洋装、束髪の普及は最も著しいもので、明治一八年九月本校も洋服を採用し、生徒は洋服で課業を受け、又学校でダンスの稽古をした」(同書24頁)という。安井の手記にも、「官立学校においてクリスマスの祝賀会を催したり、講堂において知名の紳士淑女が舞踏会を催し、有志の生徒は之れに参加することを許されたことさへあったのである」(同書25頁)とある。そして、明治一八年九月とは、その注によると森有礼の改革により女子師範学校が師範学校女子部となった同年八月のすぐ後のことであり、鹿鳴館華やかなりし頃のことになる。鏡子夫人もまた、学生時代から洋服に慣れ親しんでいたと考えられ、それを着こなしていたのであろう。
ちなみに、『安井てつ伝』は、安井と鏡子夫人との洋服姿の違いについて興味深い観察を紹介している。同じ高等師範学校で洋装の洗礼を受けた両者がどのように異なっていたのか、同書が引用している書簡集(『若き日のあと』114頁)から、紹介しよう。
(安井てつによる野口幽香宛明治32年9月11日付書簡。[ ]内は高橋が注として挿入。部分的に「、」を「。」にして引用し、またいくつか改行を施した)
「(前略)実は六月十一日より校長[トレーニング・カレッジ校長ヒュース]と共ニスヰツランド[スイス]にまゐり[中略]七週間[中略]滞在致し候」
「途中巴里にて安達かね子氏にあひ、夕飯の御馳走に相成、翌日晝飯[昼食]には私旅店[原文のまま]に同氏を招き候。
同氏は細君なり。人の母なり。巴里住ゐなり。実に奇れいにおつくりして、美しき衣服をつけ[、]しとやかにもてなす。
傍に、私は旅行中なり。書生なり。英国風に感化せられて無骨なるカラに、セイラー、ハット(書生の夏帽子)を被りてあひし候。
如何にも其差甚しく、全く仏英の特性を二人間にあらわせりとて、後に校長が笑ひ居り候。
同校長は今まで英国人が私に及ぼせる自然の感化がこれほどならんとは思はざりしとおどろき居り候。
(唯外観の感化にて内心は安達氏も私も共に日本の女子たるものを)。」
鏡子夫人(書簡の表記では「かね子」)について、①「細君」(峰一郎と婚姻している)、②「人の母」(功子・太郎・万里子の母親)、③「巴里[パリ]住」、④「実に」綺麗にお作りして、⑤「美しき衣服をつけ」⑥「しとやかにもてなす」というのも興味深いが、「無骨なるカラに」「セーラーハット」のイギリス留学生安井と比較し、これをフランスとイギリスの特性としてみている訳である。同じ日本人ではあるが、両国の感化に驚いているケンブリッジ大学のカレッジ校長ヒュースの観察眼も面白いところである。
なお、先に引用した書簡にはその続きがあり「私従兄岡村司仏国留学を命ぜられ三年間参る筈に候間帰朝前巴里にてあひ申さん」という。1899年の書簡であり、スイスに夏休みを過ごしたのはパリ万博の前年のことであるが、すでに万国博覧会を目当てにパリを再訪することを決めていたことが解る。
(以下写真引用)

お茶の水女子大学所蔵の写真を、同大学歴史資料館館長の許可をいただき、ご提供いただいた。高等師範学科卒業時の写真で明治23年(1890年)3月のもの。手前右から2人目が安井てつ(日誌では「て津子」)であり、そのことについては前掲『若き日のあと』を参照した。同書では、卒業生の特定がなされている。

同じく、お茶の水女子大学所蔵の卒業写真をご提供いただいた。それとともに、お茶の水女子大学歴史資料館の長嶋様より関連する情報もご教示いただいた。記してお礼申し上げたい。
写真は、明治24年(1891年)4月のもので、こちらは高等師範科・小学師範科卒業生のものである。卒業生は、国会図書館のデジタルコレクションにある官報(同年3月27日付第2319号)と『女子高等師範学校一覧』によれば、佐々木あさ(山口県士族)太田みつ(長野県士族)田中くに(山梨県平民)原いく(長野県平民)細野鉎(東京府士族)星名喜與(愛媛県士族)小貫琴(秋田県士族)吉田のぶ(群馬県平民)吉川鉚(新潟県士族)窪田すみ(静岡県士族)志賀かま(東京府士族)池田しの(東京府士族)戸澤かず(東京士族)三好いね(広島県士族)藤村政(山口県士族)安藤みち(千葉県士族)髙澤鏡(山形県士族)及び小学師範科卒業生の廣瀬蓁治(京都府士族)。したがって、高等師範科17名、小学師範科1名(3月卒業)となり、写真との人数は合っている。ただ、多くの方からこの人ではというご意見はいただいたのだが、確実にこの方が「かね子」夫人であるという人物特定は出来ないでいる。
夫人はもちろんのこと、同級生の方についても情報をご提供いただければ幸いです。
投稿日:2019年4月22日
2、子供たち
岡村にはこの当時子供が二人いた。亨と豊である。妻子を日本に残しての留学は「遠島も同然なり」という表現が日誌には出て来るが(1899年(明治32年)10月19日)、妻はもとより可愛い盛りの子供たちと別れての異国生活は、確かに心寂しいものであったろう。
安達夫妻にも幼い子供たちがいた。この当時、長女の功子(イサオ)は日本に残していたが、長男太郎と次女万里子の二人は手元で育てている。岡村とは違った家族団らんの生活をおくっていたと思われる。先にも触れた、パリに着いた直後の岡村の日誌には、安達の子供たちのようすが出て来る。
「午後[中略]、安達峯一郎氏の招飲に赴きぬ。来客は[中略]五人なり。[中略]和洋折衷の御馳走にて珍味いもの多かりき。安達夫婦も座に連なり、下婢二人給仕し、甚だ優渥なる饗応なりき。安達氏の細君は平常洋服を着するものと見え、一見仏人の如し。能く仏語を操る[あやつる]。小児二人、長は男子にて四歳、次は女子なりと云ふ。長男は仏語は能くすれども日本語は知らずと云ふ。これは穏婆[おそらく乳母のこと]、下女等皆仏語を用ゐるが為なり。亦奇と謂ふべし。」(同年10月24日)
最後の「奇と謂ふべし」の「奇」とは、不思議なこと、といった程度のことであろうか。日誌には別の文脈でも出て来るもの言いで、口癖に近く、悪い意味ではない。むしろ、安達の家族がフランス語に慣れ親しんでいることに驚いている感じである。大人より子供の方が言葉に慣れるのが早いことは、帰国子女が稀ではない現代ではよく知られたことであろうが、むしろ年を経ることによってそれらの言葉を忘れてしまうことの方が残念なことである。後のことではあるが、峰一郎も、長男の太郎が日本に帰国してからもフランス語を忘れないように、その勉強を励ましていることは、書簡集でも紹介されている。また、鏡子夫人がフランス語をよくしたことについても、婚姻後の勉強を励ましていることなどから知ることができる。夫人が、峰一郎の同級生から見ても「能く仏語を操る」とされていたことは、興味深いところであろう。
実は、岡村の育児に対する考えが日誌で語られている。日本に残してきた妻郁子宛の日誌であるから、当然といえば当然であるが、岡村の人となりを垣間見ることができることから、短く紹介しておきたい。
岡村は、自身のことを「随分神経質の方」であるという(1900年2月28日)。確かに、「安達の子にスエズにて購入たる玩具を贈」ったり(1899年10月27日)、下宿先の大家にクリスマスの贈り物をする(12月23日)など、細やかな心を尽くしていることを見ることができる。岡村は、そのような自分と、便りに出てくる子供たちの様子を比べ、「親の性質が子に移ること[中略]誠に驚くべし」とし、子供は「成るべくボンヤリと活発に養育するこそ好けれ」という(24日)。「子供等、成るべくぼんやりと育て玉へかし。親に似て神経質なるは宜しからず。」というのが岡村の考えのようである(先の2月28日)。詳しい教育論を展開しているわけではないが、そこに、ルソーのエミールを彷彿させるものを感じるのは私だけであろうか。おおらかに育ってほしいという親の願いを見ることができよう。
安達はどのような教育論を持っていたであろうか。子供たちとのやり取りが書簡として残されているが、詳しく見てみたい事柄の一つである。
月別アーカイブ
年別アーカイブ
サイトマップを閉じる ▲